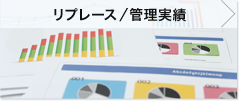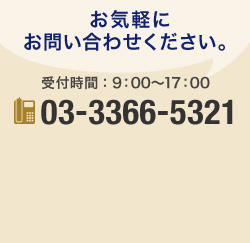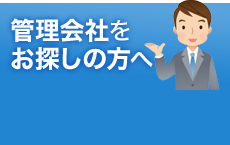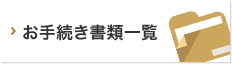江戸時代の夏
2025.08.01
連日、気温が30度を超えまさに酷暑と言える日々が続いております。
現代においては、文明の利器を活用して暑さを凌いでおりますが、江戸時代の日本においてどうやって夏の暑さを克服していたか、ふと気になり服装、食べ物、グッズについて調べてみました。
江戸時代は、夏の平均気温が現代の日本より2~3度ほど低かったそうです。現代のように地面がアスファルトで覆われていないため、太陽光の照り返しが少なく、体感温度は現代よりも低かったそうです。
まず、服装についてですが、現代のように空調服のような文明の利器は当然ながらありません。当時人気だった服装は、浴衣だそうでお風呂上りや家でくつろぐ際に着られていたそうです。
また、浴衣はくだけた服装だったらしく昼間に浴衣を着て町中を歩くのはかなりのNG行為だったそうです。次に、食べ物についてですが、現代でも食べられている鰻、ところてん等が好んで食べられていたそうです。
夏になると冷や水売りと言われる行商が水に砂糖を加え白玉をいれたものを売っていたそうです。器には、より涼しさを感じられるように真鍮や錫製のものが使われていました。現代では、冬に飲んでいるイメージが強いと思いますが、甘酒も夏に飲まれていたそうです。夏の貴重な食べ物として氷も食べられていたそうです。
氷は一般庶民ではなかなか手に入らず、専ら上流階級が食していたそうです。
最後にグッズについてですが、団扇、風鈴、蚊帳、すだれ等を使い暑さを凌いでいたようです。
こちらについては、現代においても使用されている方も多くいらっしゃるかと思われます。
江戸時代の夏の過ごし方を取り入れてみるのもたまには良いかもしれません。